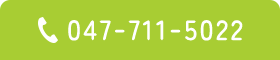便秘と下痢の診断と治療
 便秘や下痢は、私たちの日常生活でよく見られる症状ですが、これらは単なる一時的な体調不良にとどまらず、深刻な病気が原因となっている場合があります。急に便通が変わった、症状が続き治らないなど、気になることがある場合には、早めにご相談ください。
便秘や下痢は、私たちの日常生活でよく見られる症状ですが、これらは単なる一時的な体調不良にとどまらず、深刻な病気が原因となっている場合があります。急に便通が変わった、症状が続き治らないなど、気になることがある場合には、早めにご相談ください。
便秘について
 便秘は、腸内の老廃物が正常に排出されず、腸に長時間留まる状態を指します。お腹の張りが気になる、排便したのにすっきりしない、右や左の下腹部が痛むなど様々な症状も伴います。
便秘は、腸内の老廃物が正常に排出されず、腸に長時間留まる状態を指します。お腹の張りが気になる、排便したのにすっきりしない、右や左の下腹部が痛むなど様々な症状も伴います。
便秘の原因
便秘は、大きく分けて「機能性便秘」と「器質性便秘」の2種類に分類されます。それぞれの便秘には異なる原因があり、適切な診断が必要です。
機能性便秘
機能性便秘は、大腸の運動機能や水分吸収機能が十分に働かないことで起こります。ストレス、水分不足、食生活の変化、運動不足、薬の服用など様々な原因があります。
器質性便秘
器質性便秘は、腸の形態に物理的な異常があり、便が通過できなくなることで起こる便秘です。大腸がんや腸の狭窄、外科手術後や腹膜炎後の腸管癒着などが原因となります。
治療
生活習慣の改善
水分摂取を積極的に行い、食物繊維を豊富に含む野菜や果物をバランス良く摂取することを心掛けましょう。3食をきまった時間に食べることや、決まった時間にトイレに座ること、適度な運動を続けることも大切です。
食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類があり、それぞれ異なる役割を果たします。
水溶性食物繊維
水に溶けることでゲル状に変化します。腸の内容物に水分を含ませ、ゼリー状にすることで便秘解消に役立ちます。また、小腸での栄養素の吸収を穏やかにすることで血糖値の急激な上昇を防ぎます。また、コレステロールやナトリウムを体外へ排出する働きもあり、高血圧や脂質異常症の予防にも有効です。
含まれる食品例はワカメ、昆布などの海藻類、大麦やライ麦などの穀類、里芋や長芋などの芋類、アボガドやりんごなどの果物です。
不溶性食物繊維
大腸の粘膜を刺激して水分や粘液の分泌や腸管蠕動を促進します。便を柔らかくし体積を増やしたり、便が腸に長くとどまらないようにします。腸の蠕動運動が低下しておこる便秘(弛緩性便秘)には有効ですが、腸の緊張が強すぎて起こる便秘(痙攣性便秘)では逆に便秘を悪化させることがあるため注意が必要です。含まれる食品例はごぼうやブロッコリー、ほうれん草などの野菜類全般、小豆や大豆などの豆類、エリンギやしいたけなどのきのこ類です。
下剤の使用
生活習慣の改善で便秘が改善しない場合には、下剤を使います。下剤は刺激性下剤と非刺激性下剤に分けられます。当院では、便秘のタイプに応じて便を柔らかくする薬や腸の動きを改善する薬、腸内環境を整える薬など、非刺激性下剤を中心に適切な薬を選択します。
現在服用中の薬の見直し
センナやアロエ、ビサコジルやピコスルファート、大黄などを含む下剤は、刺激性下剤と呼ばれ、腸の粘膜を強く刺激して蠕動を起こさせることで便秘を解消します。週に1,2回くらいたまに使う程度であれば良く効くお薬ですが、長期間毎日使用していると腸が刺激に対して鈍くなり、下剤が効かなくなる「弛緩性便秘」という状態になってしまいます。刺激性下剤を少しずつ、非刺激性下剤へ置き換えてゆく治療が必要です。
便秘に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。当院では、症状の改善に向けた最適な治療をサポートいたします。
下痢について
 下痢は、便に含まれる水分量が通常よりも多くなり、便の形が無くなって水のような便が何度も出る状態です。飲食物に含まれる水分は大部分が小腸で吸収され、残りの1.5~2Lが大腸で吸収されます。何らかの原因で、小腸や大腸での水分分泌が増えたり、水分吸収がうまく行かなくなると下痢になります。下痢は2週間程で症状が収まる急性下痢と、4週間以上続く慢性下痢に分けられます。
下痢は、便に含まれる水分量が通常よりも多くなり、便の形が無くなって水のような便が何度も出る状態です。飲食物に含まれる水分は大部分が小腸で吸収され、残りの1.5~2Lが大腸で吸収されます。何らかの原因で、小腸や大腸での水分分泌が増えたり、水分吸収がうまく行かなくなると下痢になります。下痢は2週間程で症状が収まる急性下痢と、4週間以上続く慢性下痢に分けられます。
下痢の原因
生活習慣から起こる下痢
食べ過ぎ、飲みすぎ
特に疲労やストレスがたまっているときは、飲食物、アルコールの刺激に敏感になり下痢を引き起こすことがあります。
刺激物の過剰摂取
香辛料や過剰な脂肪分の摂取で腸の蠕動運動が活発になり下痢が発生します。
ストレス
自律神経の乱れにより腸管蠕動に異常が生じ、下痢や便秘が発生します。
疾患から起こる下痢
感染性腸炎
急性下痢症の90%は細菌やウイルス感染が原因です。ノロウイルスやロタウイルスなど流行性のウイルス、カンピロバクターやサルモネラ菌といった食中毒、赤痢やコレラと言った特定の地域で感染する旅行者下痢症が該当します。アメーバ赤痢やジアルジア症など寄生虫感染も下痢の原因になります。こまめな水分摂取や安静で、軽症な方の多くは数日で治癒することが望めますが、小さなお子さんや高齢者、体力や免疫力が低下している方、重症な方は、抗菌薬や点滴など積極的な治療が必要となります。感染性腸炎と診断された場合、感染拡大を防ぐため、ご本人だけでなくご家族にも徹底した手洗いや衛生管理をお願いしています。便や嘔吐物の処理時には手袋やマスクを使用し、二次感染を防止します。
薬剤性下痢抗菌薬や、抗がん剤、胃酸を抑える薬、糖尿病薬など様々な薬が、急性、慢性の下痢の原因となります。薬を飲み始めて少ししてから下痢が出現した場合に疑います。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
潰瘍性大腸炎、クローン病ともに腸管に慢性の炎症が起き、水分分泌が亢進したり、水分吸収が低下します。原因は不明で、国が指定する難病です。腹痛、下痢、血便をきたすことが多いですが、症状の軽いうちは下痢のみ見られることもあります。30代までの若い時期に発症することが多いですが、症状が軽いため医療機関を受診せず、中年以降に診断されることもあります。腸管の炎症が続くと、腸管の変形が進んだり、腸に穴が開く(穿孔)やがんの原因になったりするため、早期の診断・治療が大切です。
大腸がん
腸内の内容物が詰まり便秘になり、その後腸が水分分泌が亢進して下痢を引き起こすことで便秘と下痢を繰り返します。排便状況がいつもと違う場合には、念頭に置かねばならない疾患です。
過敏性腸症候群
下痢や便秘、腹痛、腹部膨満感など、多様な症状を伴う疾患です。感染性腸炎が治った後に発症することもあります。緊張やストレス、不安定な生活習慣が主な原因とされています。生活の質の低下につながるため、病院を受診し適切な診断、治療をうけることをおすすめします。
慢性膵炎・膵癌
主に過度の飲酒が原因で、膵臓にダメージが蓄積し、膵臓の機能が低下した状態が慢性膵炎です。慢性膵炎や膵癌では、膵臓からでる消化酵素の量が減り、タンパク質や脂肪をうまく吸収できなくなって下痢になります。慢性膵炎では禁酒することが治療の第一です。
下痢と併発する症状に注意
下痢は単独で現れる場合もあれば、他の症状と併発することもあります。以下のような症状が下痢に加わる場合、重篤な疾患が潜んでいる可能性がありますので、注意が必要です。
- 吐き気、嘔吐、発熱を伴う
- 下痢に血が混じっている
- 強い腹痛がある
- 下痢が長く続く、どんどんひどくなる
- 喉が乾く、皮膚が乾燥する、尿量が少ない
これらの症状がある場合は、早急に医療機関受診をおすすめします。