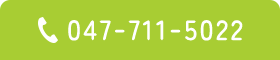胃カメラでわかる胃の病気
急性胃炎
 急性胃炎は、アルコールの過剰摂取、痛み止めや抗菌薬の服用、ストレスなどが原因となることが多い疾患です。みぞおちの痛みなど胃炎の症状が現れた場合、急性胃炎が疑われます。
急性胃炎は、アルコールの過剰摂取、痛み止めや抗菌薬の服用、ストレスなどが原因となることが多い疾患です。みぞおちの痛みなど胃炎の症状が現れた場合、急性胃炎が疑われます。
内視鏡検査を行い、胃粘膜の状態を確認することで正確な診断が可能です。診断結果に基づいて適切な治療を行うことで、症状改善が期待されます。気になる症状がある方は、早めの受診をお勧めいたします。
慢性胃炎
慢性胃炎は、ピロリ菌感染などが原因で胃粘膜に慢性的な炎症が生じた状態です。この炎症が続くと、粘膜のびらんや潰瘍が繰り返し発生し、慢性的な不快感の結果、日常生活に支障がでることがあります。
慢性胃炎が続くと、胃粘膜が萎縮する「萎縮性胃炎」が進行し、胃の粘膜が腸の粘膜のような変化を起こす「腸上皮化生」という状態になります。。「腸上皮化生」は、胃がんの前段階の状態とされており、発がんの危険性が高くなります。胃がん患者様の多くにピロリ菌感染が認められていますが、除菌治療により胃粘膜の状態が改善し、胃がんのリスクを低下させることが可能です。
胃潰瘍
胃潰瘍は、胃粘膜が深く傷ついた状態を指し、主な原因として以下が挙げられます。
- ピロリ菌感染
- アルコールの過剰摂取
- 痛み止めや一部の抗血栓薬の内服
- 胃がんなど悪性腫瘍
多くは抗潰瘍薬による治療が効果的です。また、ピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療を行うことで潰瘍の再発を予防することが可能です。放置すると出血や穿孔(胃や腸の壁に穴があくこと)のリスクが高まるため、早めの受診と適切な治療が大切です。
胃ポリープ
胃にできるポリープには以下の種類があります。
胃底腺ポリープ
ピロリ菌感染などの炎症がない胃粘膜にできます。がん化するリスクはほぼ無いため、切除は行わず経過観察で問題ないことがほとんどです。
過形成性ポリープ・炎症性ポリープ
ピロリ菌感染など胃粘膜に慢性の炎症がある場合にできます。ピロリ菌感染を伴う事が多く、胃カメラで過形成性ポリープが見つかった方は、ピロリ菌検査をおすすめします。過形成性ポリープからのがん化率は1~3%と言われており、過形成性ポリープと診断された方は定期的な胃カメラをおすすめします。
ポリープの種類は、内視鏡検査中に組織を採取して生検を行い、確定診断を行います。当院では、患者様に安心して治療を受けていただけるよう、最新の設備と経験豊富なスタッフによる診療を行っております。
胃ポリープが見つかった場合でも、ほとんどが経過観察で対応可能です。不安なことがございましたら、当院までお気軽にご相談ください。
胃がん
胃がんは、がんの中でも日本では発症数と死亡数が多い疾患ですが、近年では内視鏡技術の進歩により早期発見・早期治療が可能となり、完治を目指せる病気になっています。
胃がんの多くは、ピロリ菌感染による慢性胃炎が進行して発生すると考えられています。慢性胃炎が萎縮性胃炎へと進行し胃がんリスクが高まります。そのため、ピロリ菌感染の有無を調べ、陽性の場合には早期に除菌治療を受けることが推奨されます。
胃がんが胃の壁の浅い位置にとどまり、胃の外側のリンパ節への転移がない状態で発見された場合、内視鏡を用いた切除が可能です。この方法はお腹を切る手術と比べて体への負担が少なく、日常生活への影響も軽くて済みます。ピロリ菌感染陽性の方、除菌治療を受けた方、家族に胃がんの病歴がある方、慢性胃炎を指摘された方は胃がんのリスクが高まるため、胃がん早期発見のため定期的な内視鏡検査を受けることが重要です。
ピロリ菌感染
 ピロリ菌は主に幼少期に感染するとされ、成人してからの感染はまれです。感染経路としては、汚染された井戸水の飲用や家庭内での接触による人から人への感染が挙げられます。感染したピロリ菌は、周囲の胃酸の強酸性環境を中和することで胃に住み着きます。
ピロリ菌は主に幼少期に感染するとされ、成人してからの感染はまれです。感染経路としては、汚染された井戸水の飲用や家庭内での接触による人から人への感染が挙げられます。感染したピロリ菌は、周囲の胃酸の強酸性環境を中和することで胃に住み着きます。
ピロリ菌は毒素を分泌し、慢性胃炎(萎縮性胃炎や腸上皮化生)を引き起こします。これが進行すると、胃がんの発症リスクが高まることが知られています。ピロリ菌は治療によって除菌可能であり、除菌が成功すると慢性胃炎の改善がみこめます。また、早期に除菌を行うことで次世代への感染予防にもつながります。
ピロリ菌感染の有無は、血液検査や呼気検査、便検査等で行います。ピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療の対象となります(保険適用のためには胃カメラが必要です)。除菌治療を行うことで胃粘膜の炎症を抑え、胃がんリスクを低減する効果が期待できます。
当院では、痛みや苦痛を最小限に抑えた内視鏡検査を行っております。また、ピロリ菌に関するご質問や保険診療に関する疑問にも丁寧にお答えしております。安心して検査や治療を受けていただける環境を整えておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
胃カメラでわかる食道の病気
逆流性食道炎
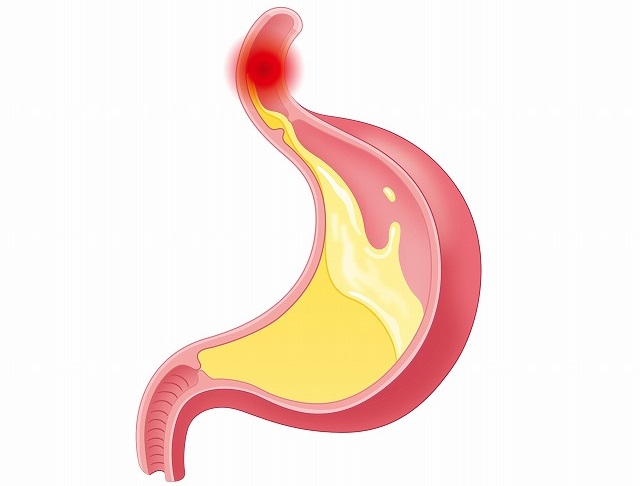 逆流性食道炎は、胃液やそれを含むものが食道へ逆流し、粘膜に炎症を引き起こす病気です。主な症状として次のようなものがあります。
逆流性食道炎は、胃液やそれを含むものが食道へ逆流し、粘膜に炎症を引き起こす病気です。主な症状として次のようなものがあります。
- 胸焼け
- 呑酸(酸味や苦みのあるものがゲップと共に上がってくる)
- みぞおちの痛み
- 咳やのどの違和感(心疾患と似た症状を引き起こすこともあります)
この疾患は、食生活の乱れや腹部を締め付ける衣類、猫背などの姿勢、ストレスなどの生活習慣に起因することが多く、再発しやすい特徴があります。
逆流性食道炎は、薬物治療によって症状を効果的に抑えることが可能です。しかし、再発を防ぐためには生活習慣の改善が欠かせません。また、炎症を繰り返すとバレット食道へ進行し、食道がんのリスクが高まるため、定期的な検査が重要です。当院では患者様の生活習慣を考慮した治療とアドバイスを行い、症状の改善と再発予防をサポートしています。
バレット食道
バレット食道は、逆流性食道炎による慢性的な炎症で、食道の粘膜が胃の粘膜に似た形へと変化する病気です。この状態は食道腺がん(バレット腺がん)の発生リスクが高いことが知られています。欧米では、食道がんの多くが逆流性食道炎からバレット食道を経て発生した食道腺がんです。日本でも近年の食生活の欧米化により、バレット食道が増加傾向にあります。
逆流性食道炎やバレット食道がある場合には、内視鏡検査で状態を定期的に確認し、食道がんを早期に発見することが重要です。
食道がん
食道がんは初期には無症状ですが、進行すると以下のような症状が現れます。
- 胸焼け
- 胸やみぞおちの違和感
- 飲み込みにくさやつかえ感
食道がんになりやすいのは、、お酒をたくさん飲む人、お酒を飲むとすぐ顔が赤くなる人、タバコを吸う人、バレット食道のある人です。男女別では男性に多く、50歳以上の年齢で増加します。これらに該当する方は定期的な検査をおすすめします。
早期発見ができれば、内視鏡治療が可能です。一方で進行すると、外科手術や放射線、抗がん剤と言った、身体への負担が大きくなる治療が必要となるため、少しでも違和感がある場合は早めの受診をおすすめします。
胃カメラでわかる
「のど」の病気
胃カメラでは、食道より上に位置する「咽頭」の状態も確認可能です。咽頭は次の3つに分けられます。
- 上咽頭(鼻の奥の空気の通り道)
- 中咽頭(空気と飲食物が通る部分)
- 下咽頭(食べ物を食道に運ぶ部分)
咽頭がんは、発生部位に応じて上咽頭がん、中咽頭がん、下咽頭がんに分類されます。早期発見であれば内視鏡による切除が可能ですが、進行すると外科手術や放射線治療が必要となり、発声や食事に影響が出る場合があります。当院では胃カメラの際に咽頭粘膜の観察も行い、咽頭がんの早期発見に努めています。