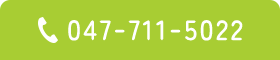- 胸焼け、ゲップ、喉のつかえがある…逆流性食道炎の心配は?
- 逆流性食道炎の原因
- 逆流性食道炎になりやすい人の特徴
- 逆流性食道炎の症状チェック
- 逆流性食道炎の検査
- 逆流性食道炎の治療
- 逆流性食道炎になったらやってはいけないこと
胸焼け、ゲップ、喉のつかえがある…逆流性食道炎の心配は?

逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流して食道粘膜に炎症が起こる病気です。通常、食道と胃の間にある括約筋が胃酸の逆流を防いでいますが、この括約筋の働きが弱くなることで逆流が生じ、炎症が起こります。
逆流性食道炎では、以下のような症状が現れます。
- 胸やけ
- ゲップ
- 酸っぱいものがこみ上げてくる呑酸
- みぞおちの痛み
- のどのつかえ感
- 咳や声枯れ
これらの症状が慢性的に続き日常生活に支障をきたし得るため、きちんとした治療が必要です。
逆流性食道炎は、薬物療法によって比較的短期間で症状の改善が期待できます。ただし、生活習慣の乱れにより再発しやすい傾向があり、特に食道の炎症が慢性化すると、食道がんのリスクが高まる可能性があります。そのため、適切な治療に加え、生活習慣の見直しが必要です。
当院の消化器内科では、患者様一人ひとりの症状に合わせた丁寧な治療を提供しています。また、再発予防のための生活習慣のアドバイスも行っております。気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。
逆流性食道炎の原因
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流し、食道粘膜に炎症が起きる病気です。この病気の原因にはいくつかの要因が考えられます。まず、加齢や肥満などで、食道と胃の境目にある下部食道括約筋が弱まり胃酸が逆流しやすくなる「食道括約筋の機能低下」が挙げられます。また、ストレスなどによって自律神経が乱れると、胃酸の分泌が過剰になり、逆流を引き起こす「胃酸分泌の増加」も原因となります。
さらに、暴飲暴食や早食い、食後すぐに横になるといった「生活習慣の乱れ」も逆流を助長する要因の一つです。姿勢や体型も影響を及ぼし、猫背や前かがみの姿勢、肥満、妊娠といった腹圧上場は逆流リスクを高めます。また、食道と胃は横隔膜に空いた穴を通じてつながっていますが、この穴(食道裂孔)胃が食道側へはみ出す「食道裂孔ヘルニア」も逆流性食道炎の発症に関与しています。
ストレスを適切に管理し、日々の生活習慣を整えることで逆流性食道炎の発症リスクを低減し、症状の改善も期待できます。
逆流性食道炎になりやすい人の特徴
逆流性食道炎は、以下のような生活習慣や体型、姿勢の特徴を持つ方に発症しやすい傾向があります。
- 食べ物をよく噛まずに飲み込む
- 早食い
- 食べてすぐ横になる
- 便秘
- 喫煙習慣
- 肥満
- 妊娠中
- お腹を締め付ける服装やベルトの使用
- 長時間前かがみになる姿勢
- 加齢による腰の曲がり
逆流性食道炎の症状チェック
流性性食道炎になっている、なりやすい人には、以下のような症状が現れることがあります。
- 胸やけ
- 胃もたれ
- ゲップ
- 吐き気・嘔吐
- のどのつかえ感
- のどがヒリヒリする
- すぐに満腹になる感覚
逆流性食道炎の検査

「胸やけ」や「胃のムカムカ」といった症状は、逆流性食道炎以外の疾患でも起こり得るため、正確な診断には内視鏡検査が必要です。内視鏡検査では、細い管状のカメラを使用して食道内を直接確認し、胃酸が逆流しているか、その影響で炎症が生じているかを詳しく調べることができます。さらに、食道裂孔ヘルニアや食道がんの可能性についても同時に確認できます。
当院では、痛みに配慮し快適に受けられる内視鏡検査を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎の治療には、薬物療法に加え、生活習慣の改善が欠かせません。適切な治療は、再発予防だけでなく、合併症であるバレット食道や食道がんのリスク軽減にもつながります。
生活習慣
食習慣を整える
脂肪分や糖質の過剰摂取を控え、腹八分目を心がけましょう。特に食後すぐに横になることは避け、最低でも3時間空けてから就寝するようにしてください。香辛料や酸味の強い食品、消化に悪い食品も控えることで胃への負担が軽減され、症状の改善が期待できます。
肥満を解消する
肥満を解消し、衣服によるお腹への締付をへらすことが逆流の予防につながります。
姿勢に注意する
姿勢と胃酸の逆流は深く関係しています。日中は姿勢を良くして過ごしましょう。
タバコ・カフェイン・アルコールを控える
タバコやカフェインは胃酸分泌を促進します。さらにアルコールは食道括約筋をゆるめる作用があり、いずれも逆流性食道炎を悪化させる要因です。禁煙を心がけるとともに、コーヒーや緑茶の摂取を減らす、アルコールを控えるよう意識しましょう。
薬物療法
逆流性食道炎の治療では、症状に応じて胃酸の分泌を抑える薬や食道粘膜を保護する薬などを使用します。当院では患者様一人ひとりの症状に合わせて適切な処方を行っております。
酸分泌抑制薬PPI(プロトンポンプ阻害薬)
胃酸の分泌を抑え、食道へ逆流する胃酸を少なくすることで炎症を軽減する薬で酸分泌抑制薬には、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)、カリウムイオン競合型酸ブロッカー(PCAB)があります。再発予防にも効果が期待でき、逆流性食道炎の治療でよく使用されます。
消化管運動機能改善剤
消化管の運動を促進し、胃の中の滞留を減らして逆流を防ぎます。酸分泌抑制薬に比べ、単独での効果は弱いですが、併用することで治療の上乗せ効果が期待できます。
粘膜保護薬
食道粘膜を保護し炎症を改善します。他の薬と併用されることが多いです。
粘膜保護薬
食道粘膜を保護し炎症を改善しますが、効果の持続が短いため、他の薬と併用されることが多いです。
逆流性食道炎になったらやってはいけないこと
逆流性食道炎を改善・予防するためには、以下の行動を控えることが重要です。
- 食後すぐに横になる
- 就寝前の大量の食事(飲酒も含む)
- 刺激物の摂取
- ストレスや疲労の蓄積